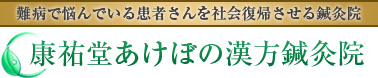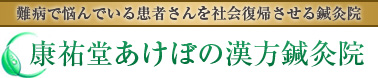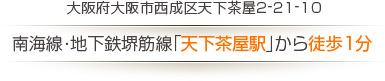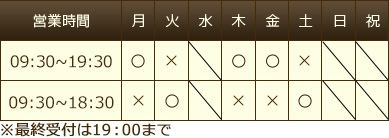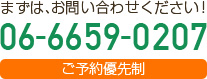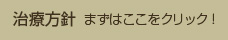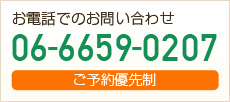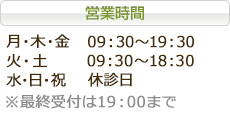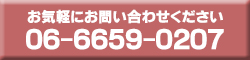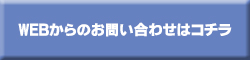統合失調症⑥治療方法について〜薬物療法編〜
副作用かな? と思ったら
時として体が硬くなったように感じたり、手足がふるえたり、落ち着きがなくなる人も中にはいます。また、のどが渇いたり、便秘になったりする人もいます。
これらは薬の副作用の場合がありますので、少しでも「おかしいな」と感じたら主治医に相談しましょう。薬の量を調整したり、種類や組み合わせを変えることで、副作用を抑えることが可能です。
服薬をやめてもいいですか?
薬を飲むことをやめると、再び症状が出てくることがあります。また、再発を繰り返すと症状が強くなり、治りにくくなります。薬には再発を予防する作用がありますから、薬を続けることはとても重要です。
症状が良くなったからといって、勝手に自分で薬をやめてはいけません。毎日薬を飲むのが面倒であれば、1 回の投与で2~4週間効果が続く持続性注射剤を選ぶこともできます。薬を飲むことをやめる、薬の量を減らすなどについては、主治医とよく相談して決めましょう。
統合失調症の代表的な治療として、薬による治療と精神科リハビリテーションがあります。
急性期には薬による治療が基本になりますが、なるべく早い時期から薬と精神科リハビリテーションを組み合わせた治療を行うことが効果的です。
〜薬物療法について〜
○抗精神病薬
統合失調症の治療の中心となる薬を「抗精神病薬」といい、症状の改善や再発の予防に大きな力を発揮します。抗精神病薬は、主として脳内で過剰に活動しているドーパミン神経の活動を抑えることで症状を改善すると考えられています。抗精神病薬は、定型抗精神病薬(従来型)と非定型抗精神病薬(新規)とに分けられます。定型抗精神病薬は陽性症状に効果があり、非定型抗精神病薬は陽性症状に加えて陰性症状や認知機能障害に対する効果も期待できます。
抗精神病薬のほかに症状に合わせて、不安や抑うつを和らげる薬、睡眠薬などが使われます。また、抗精神病薬の副作用を抑えるための薬が処方される場合もあります。
○症状を調整する薬
抗不安薬 強い不安感や緊張感を和らげる
抗うつ薬 憂うつな気分を和らげ、意欲を高める
睡眠薬 よく眠れない、寝付きが悪い、早朝に目が覚めてしまう、昼夜逆転など、睡眠のリズムを調整する、など、、、
統合失調症は病気の経過により、前兆期・急性期・消耗期(休息期)・回復期に分けられます。それぞれの病期で特徴的な症状が認められます。
前兆期
特に目立った症状はありませんが、何となく変だと感じるようになります。
眠れなかったり、イライラしたり、集中力が低下するなどの症状が続きます。
急性期
幻覚や妄想など不思議な体験をするので、自分の中で何かが変だと感じながらも、自分が病気だと思えず、他人から見ておかしな行動をすることがあります。また、周りの出来事に敏感になり、不安や緊張を強く感じたりします。
消耗期(休息期)
幻覚や妄想などの目立った症状は少なくなりますが、元気がなくなったり、やる気が起こらなくなったりします。
これは、急性期に心と体のエネルギーをたくさん使ってしまったことが原因と考えられていますので、薬を飲み続けながら、ゆっくりと十分に休むことが必要です。
回復期
少しずつ元気が出てきて心も体も安定してきますので、焦らず、ゆっくりと生活の範囲を広げていきましょう。
また、再発予防のために薬を忘れずに飲むことが大切です。
はっきりとした原因は不明ですが、一説によると脳の神経伝達物質のバランスが崩れて混乱することが関係しているといわれています。この他に遺伝、環境因子など、いくつかの要因が考えられるも、すべて可能性の域を出ません。原因は1つと決められず、いくつかの危険因子が重なることで発症すると考えられています。病気になりやすい脆弱性があるところにストレスの多い環境などが重なることで発症しやすくなるとも考えられています。
日本での統合失調症の患者数は約80万人といわれています。また、世界各国の報告をまとめると、生涯のうちに統合失調症を発症する人は全体の人口の0.7%と推計されます。100人に1人弱。決して少なくない数字です。それだけ、統合失調症は身近な病気といえます。
統合失調症の症状は大きく「陽性症状」「陰性症状」「認知機能障害」の3つに分けることができます。
健康なときにはなかった状態が表れる陽性症状と、健康なときにあったものが失われるのが陰性症状です。
○陽性症状
妄想
「テレビで自分のことが話題になっている」「ずっと監視されている」など、実際にはないことを強く確信する。
幻覚
周りに誰もいないのに命令する声や悪口が聞こえたり(幻聴)、ないはずのものが見えたり(幻視)して、それを現実的な感覚として知覚する。
思考障害
思考が混乱し、考え方に一貫性がなくなる。会話に脈絡がなくなり、何を話しているのかわからなくなることもある。
○陰性症状
感情の平板化(感情鈍麻)
喜怒哀楽の表現が乏しくなり、他者の感情表現に共感することも少なくなる。
思考の貧困
会話で比喩などの抽象的な言い回しが使えなかったり、理解できなかったりする。
意欲の欠如
自発的に何かを行おうとする意欲がなくなってしまう。また、いったん始めた行動を続けるのが難しくなる。
自閉(社会的引きこもり)
自分の世界に閉じこもり、他者とのコミュニケーションをとらなくなる。
○認知機能障害
記憶力の低下
物事を覚えるのに時間がかかるようになる。
注意・集中力の低下
目の前の仕事や勉強に集中したり、考えをまとめたりすることができなくなる。
判断力の低下
物事に優先順位をつけてやるべきことを判断したり、計画を立てたりすることができなくなる。
〜統合失調症とは〜
統合失調症は脳の様々な働きをまとめることが難しくなるために、幻覚や妄想などの症状が起こる病気です。考えや気持ちがまとまらなくなる状態が続く精神疾患で、その原因は脳の機能にあると考えられています。
約100 人に1 人がかかるといわれており、決して特殊な病気ではありません。
思春期から40歳くらいまでに発病しやすい病気です。
薬や精神科リハビリテーションなどの治療によって回復することができます。
パーキンソン病が進むと嚥下(飲み込み)障害によって、水分にむせやすくなったり、食べ物がのどに詰まりやすくなったりします。そこで、調理の際は舌でつぶせる程度の硬さにして小さく切っておきます。また、焼くより煮る方が柔らかく仕上がり、あんかけなどのとろみのついた料理は食べやすくなります。食べる際には一口の量を少なくし、口の中のものを全部飲み込んでから次のものを入れるようにします。
次のようなものは詰まりやすい、またはむせやすい食品で、食べる時には注意が必要です。
①水分が少ないためパサつくもの(クッキー、カステラ、パンなど)
②粘り気があるもの(もち、団子など)
③弾力があり、かみにくいもの(こんにゃく、イカ、タコなど)
④一口で口に入ってしまい丸飲みになりやすいもの(にぎり寿司、一口大のまんじゅうなど)
⑤口の中に貼り付きやすいもの(のり、わかめなど)
⑥小さくて気管に吸い込んでしまいやすいもの(豆類など)
⑦かんでいるうちに、水分が出てきてむせやすいもの(高野豆腐、油揚げなど)
〜運動編〜
歩ける人はウォーキングを毎日20~30分を目安に行い、体力を保ちます。パーキンソン病では、歩幅や腕の振りが小さくなったり、前かがみになりやすく、つま先から着地するので転びやすくなります。歩行のリハビリでは、意識して腕を大きく振り上げ、ひざを上げ、歩幅を大きくしてかかとから着地するようにします。歩こうとしてもなかなか第一歩を踏み出せない「すくみ足」がある場合は、「1・2、1・2」と声を出すと、脳のリズムをとる働きが補われて歩きやすくなります。周りの人に声をかけてもらったり、音楽に合わせるのもよいでしょう。リズム感の訓練には、行進曲のようなリズムのはっきりした音楽を聴くだけでも効果があります(音楽療法)。音楽と一緒にメトロノームを鳴らしてリズムを刻みながら、大きな動作で歩く訓練をするのも効果的です。
〜話し言葉編〜
パーキンソン病では口やのどの動きが障害されるため、声が小さくなったり、言葉が出にくくなったりします。そのため、話し言葉のリハビリも大切です。自分でできるリハビリには、「本や新聞を大声で読む」「会話の機会を増やす」「カラオケで大声で歌う」などがあります。自分では声が小さくなっていることに気付きにくいので、やりすぎかと思うほど大きな声を出したり、ゆっくり話すよう心がけるとよいでしょう。患者さんの声が小さい場合は、家族が意識して大きな声でゆっくり話すようにすると、自然に大きな声で話すようになります。また、会話する機会を増やして、多く話してもらうのもよいでしょう。
言語聴覚士が指導する専門的な言葉のリハビリが行われている施設もあり、高い効果が実証されています。関心のある人は医師に相談してください。
規則正しい生活を送り、睡眠がしっかりとれるようにしましょう。
睡眠不足はよくありません。どうしても眠れない場合には、主治医に相談してくすりを飲むこともよいでしょう。
なるべく外に出るなど、日頃からまめに身体を動かしましょう。
パーキンソン病患者さんの日常生活を過ごしやすくするため、環境整備や道具の工夫が必要となることもあります。家族の方も、患者さんとともに、どのような工夫が必要か考えてください。
デバイス補助療法
パーキンソン病の治療を5~10年続けているうちに、ウェアリングオフやジスキネジアなどの運動合併症が出てくるなど、十分な治療が難しくなることがあります。
従来の薬物療法を行っても十分な効果が得られない場合に検討されるのが、デバイス補助療法です。DATには、専用ポンプとチューブを使って薬剤の吸収部位である小腸に直接持続的に薬剤(L-ドパ)を送り届けるL-ドパ持続経腸療法と、手術により脳の深いところに細い電線を挿入し、電気信号(パルス)を送ることによって脳を刺激し症状の改善をはかる脳深部刺激療法があります。DATは、全ての患者さんに向いているわけではないので、使用については、そのリスクとベネフィットを十分に検討する必要があります。