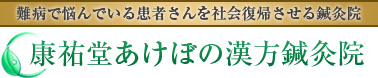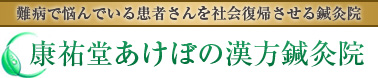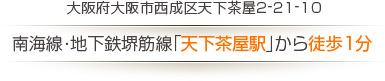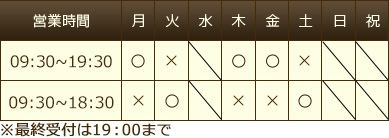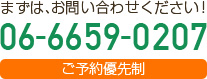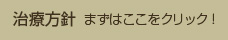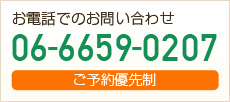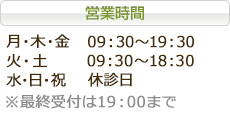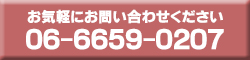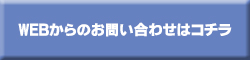クモ膜下出血 その8 最適な手術法とは
こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。
前回は「クモ膜下出血の予兆」というテーマでお話ししました。
今回は「最適な手術法とは」というテーマでお話していきます。
さて、脳MRI(MRA)で破れる前のコブ(未破裂脳動脈瘤)が見つかった場合、「治療をせずに経過を見る」と「破裂を防ぐための手術をする」という2つの選択肢があります。選択のポイントはコブの大きさで、直径5〜7mmがひとつの目安となります。
コブの形状(ヘチマ型は丸型に比べ破れやすい)やコブのできている場所にもよりますが、直径3〜4mm以下の年間破裂率は0.3%と極めて低いので、ほとんどのケースでは様子を見ることになります。その後は、年に1回検査を受ければ十分ですが、年齢や家族歴などを考慮して、もう少し慎重に見守ることもあります。
通常、直径2mm大のコブが1年で7mm以上に大きくなることはないので、あまり神経質になる必要はありません。この段階では禁煙したり、食事を見直したり、適度な運動で血圧コントロールするなど、毎日の生活習慣を改善することのほうが重要になります。コブがあることに対して神経質になり過ぎないようにし、ストレスをためないようにすることも大切です。
コブが直径5mm以上になると、手術も視野に入ってきます。さらに、直径7mmを超えたら具体的に手術の検討を始める時期です。
現在、手術法は「開頭クリッピング術」と「コイル塞栓術」が主流となっています。開頭クリッピング術は安全性が高く、後遺症が出にくい手術法です。またコイル塞栓術は体への負担が軽い、新しい治療法です。
手術はどちらか一方、またはこの2つを組み合わせて行なうこともありますが、いずれの手術法も長所・短所があるので、担当医と納得がいくまで話し合い、選択しましょう。
さて、今回でクモ膜下出血のお話は終了させていただきます。今までお読みくださりありがとうございました。
脳梗塞、脳出血、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院
院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)
〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10
TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com
こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。
前回は「クモ膜下出血が起こるとどうなる?」とはどんな病気についてお話ししました。
今回は「クモ膜下出血の発症リスク」というテーマでお話していきます・
さて、「クモ膜下出血」には、次のようになりやすいタイプがあります。
1.両親や兄弟など、家族に「クモ膜下出血」を起こした人がいる
2.血圧が高い
3.喫煙をしている
以上の3つに当てはまる人は、当てはまらない人よりも、「クモ膜下出血」になるリスクが高いと言われています。
この3つについては次回以降詳しく説明していきますが、この他にも注意したいことがいくつかあります。
まず、「クモ膜下出血」の発症が多くなるのは、40代以降ということです。これは年齢を重ねるごとに増える傾向にあります。50〜70才代になると男性より女性に多くなっていくのが特徴ですが、なぜ、女性の方が男性よりも「クモ膜下出血」になりやすいのかは、はっきりと解明はされていませんが、脳の血管の性差や、ホルモンの違いが関係すると考えられています。
また、「酒は百薬の長」といわれる飲酒についてもリスクは伴います。飲酒の量と比例して「クモ膜下出血」の発症のリスクが高くなるというデータもあるからです。血流を促し、ストレスを解消するお酒も、ほどほどに飲んでこそ効果があります。深酒にならないように自制しましょう。
いずれにしても「クモ膜下出血」は、遺伝と血圧、喫煙の3つのリスクを減らすことが一番の予防法です。そして発作の前兆を見逃さず、1分でも速く治療を進められるかが」生死の分かれ道にもなります。「クモ膜下出血」のことをよく知って、危険に備えるようにしてください。
今回はここまでです。次回は「第1のリスクー遺伝」というテーマでお話していきます。
脳梗塞、脳出血、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院
院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)
〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10
TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com
こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。
前回は「クモ膜下出血」とはどんな病気についてお話ししました。
今回は「クモ膜下出血が起こるとどうなる?」というテーマでお話していきます・
さて、それでは、「クモ膜下出血」が起こるとどうなるのでしょうか?
動脈瘤には、太い動脈から動脈血が流れてきているため、破裂と同時に多量の血液がクモ膜下腔に急激に広がります。
前回お話ししたように、脳は脳脊髄液によって一定の圧に保たれていますから、そこに多量の血液が流入すれば、脳内の圧が異常に高くなってしまいます。時間が経過する共に脳は水分を含んで腫れ、脳内の圧はさらに高くなり、脳内の血管は圧力に逆らって十分な血液を脳に供給することが難しくなります。
こうなると脳の様々な機能は正常に働かなくなってきます。意識が悪くなって昏睡状態に陥ったり、呼吸が不規則になるなどの症状が起こり、さらに、脳内の圧力が増せば増すほど脳は損傷していき、最悪の場合には瞳孔が開き、やがて呼吸が停止してしまいます。
「クモ膜下出血」になると、まずはこのような初期の脳損傷が起こり、ついで再出血や脳血管のれい縮(けいれんして収縮すること)によって命の危険が高まります。
加えて手術時の合併症のリスクもないとはいえません。いったん「クモ膜下出血」になると死亡率は30〜40%、再出血を起こせば50%にも及ぶといわれ、たとえ命が助かったとしても、植物状態になったり、マヒや失語といった後遺症に悩むケースも多く見られます。
なお、再出血は1回めの出血(脳動脈瘤の破裂)を起こした同日に起こることが最も多いため、発作が見られたらすぐさま病院に行き、治療を受けることが何よりも大切です。
今回はここまでです。次回は「クモ膜下出血の発症リスク」というテーマでお話していきます。
脳梗塞、脳出血、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院
院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)
〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10
TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com
こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。
今回から何回かに分けて、クモ膜下出血についてお話ししていきます。
まずは「クモ膜下出血」とはどんな病気についてお話していきます。
さて、「クモ膜下出血」という病名は聞いたことがあるけれど、クモ膜下の正確な場所を知っている人は、あまり多くないかもしれません。
脳や脊髄は、何層かの薄い膜によって覆われています。膜の役割は、大切な脳や神経の束ともいえる脊髄を守ることで、これらの膜は3つに分かれており、外側から硬膜、クモ膜、軟膜の順番となっています。脳や脊髄の表面をおおう軟膜とクモ膜の間にはわずかなすき間があり、この部分をクモ膜下腔と呼んでいます。
クモ膜下腔は無色透明の脳脊髄液で満たされており、やわらかなクッションのようになっています。そして、衝撃から脳や脊髄を守ったり、脳や脊髄内の圧を一定に保つ役目をしているのです。
脳の表面には、脳へ栄養や酸素を補給するための血管など、太い動脈が何本も走っていて、これらの動脈が分岐する、枝分かれしたところには血流の圧力がかかるため、コブ(脳動脈瘤)ができやすくなっています。脳動脈瘤が小さな間はよいのですが、コブが大きくなって破裂すると、クモ膜下腔に血があふれ出してしまいます。このような状態を「クモ膜下出血」といいます。
今回はここまでです。次回は「クモ膜下出血が起こるとどうなるの?」というテーマでお話していきます。
脳梗塞、脳出血、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院
院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)
〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10
TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com
こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。
前回は、「リハビリテーション病棟の取り組み」というテーマでお話ししました。
今回は、「退院の方向決定と準備」というテーマでお話ししていきます。
さて、一般的に、リハビリテーションの日々を過ごす中で、患者さんもがんばるほどに貝吹に対する悩みや葛藤が出てきます。患者さんの声はチーム内で共有し、それを解決できないか、たくさんの時間をかけて差横断します。話し合うことで意外なアイデアが生まれたり、話すだけでやりやすくなったりと、報告と連絡と相談はじつにいろいろな効力があるものです。
そして入院期間も半分を過ぎたころから退院の方向決定と準備を始めていきます。自宅退院する場合には社会資源の利用がスムーズにできるよう橋渡しもしていきます。前にお話ししたように、退院前にケアマネージャーやリフォーム業者を交えて自宅訪問指導をするのもその一つです。自宅に帰るには患者さんの歩行能力やトイレ自立が重要視されます。麻痺が強くて多少の不自由があっても環境や家族の協力に恵まれ自宅に帰ることのできる患者さんもいますし、せっかく自立レベルまで回復しても家族の事情や自己満足感にギャップがあって自宅に戻れず、療養型病院に転院したり施設に入ったりする患者さんもいます。
また、自宅に帰って逆に出来ないことが増える場合も稀にあります。コミュニティーのなかで、理解ある人と環境に囲まれるということはシンプルなようで、じつは困難であったりします。自宅でも施設でも、少しでも満たされるよう設定し、変わりうることに柔軟に対応していくことがいちばん大切でしょう。患者さんの脳が環境の変化に適応できない場合には、外的な環境を患者さんに合わせていくことが必要なことも多々あります。それを整えていくのもリハビリテーションチームの大切な役割です。
今回はここまでです。次回は「チームリハビリテーションの実例」というテーマでお話ししていきます。
脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院
院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)
〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10
TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com
こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。
前回は、「最新のリハビリテーションのために」についてお話ししました。
今回は、「リハビリテーション開始」というテーマでお話ししていきます。
さて、入院翌日から患者さんは、毎朝パジャマからトレーニングウェアに着替え、ベッドから離れ早速リハビリテーションに励むことになります。診察の結果からリハビリテーションの内容を医師が作成し、セラピストが理学療法、作業療法、言語聴覚療法という各分野から実際の専門的なリハビリテーションを始めます。具体的を内容はセラピストが患者さんの日々の変化や回復具合をじっくり観察しながら柔軟に対応していきます。
セラピストによる治療の視点は一人ひとりの患者さんの状態を深く観察し、運動の回復を促していくことです。脳卒中になったことで患者さんのからだは両側が強調して動かず、姿勢のコントロールが崩れ、麻痺側の手足を機能的に動かせなくなっています。
このような姿勢コントロール障害の肺経の一つに、痙性(けいせい)や弛緩(しかん)といった、病的な姿勢緊張状態があげられます。これは、からだの一部を他人が動かして、筋肉が収縮したときや反対の方向に伸ばしたりするときに他人が感じる抵抗のことです。健常時より抵抗感が強くなっていれば痙性、弱くなっていれば弛緩といいます。さらに筋肉や皮下組織の短縮や萎縮という二次的要素も混在してくるので、複雑になっています。セラピストはこの異常を改善しながら、姿勢コントロールを整え歩行や手足の機能改善をめざしていきます。
たとえば痙性は、脳や脊髄が能動的に働くことにより減弱すると考えられているので、セラピストは患者さんの脳の機能回復を意識しながら、手を握ったりからだを支えたりすることで感覚の刺激を入れ、機能的な運動ができるように誘導していきます。さらに機能回復は、このような経験をくり返していくことで促進されます。
また、麻痺した筋肉や皮下組織が短縮したり萎縮したりしていることに対しては、運動中に動きやすい範囲を増やしたり、患者さん自身の体重を自分で支えられるよう介助したりすることで、改善と進行予防を目指します。姿勢を保つための筋肉の緊張というものは、寝ているときや座っている時などの安静時と、歩行やものを取る動作などの活動場面とでは大きく変化するものなので、セラピストは、リハビリテーション室だけでなく、病室やトイレやお風呂や屋外など、さまざまな環境と状況のなかで患者さんを観察し、リハビリテーションを重ねていきます。
今回はここまでです。次回も引き続き「リハビリテーションの開始」というテーマでお話ししていきます。
脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院
院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)
〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10
TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com
こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。
前回は、「リハビリテーション病院における検査」についてお話ししました。
今回は、「リハビリテーション病院における機能検査」についてお話ししていきます。
さて、実際に脳がどの程度働いているのかを調べるのが機能検査です。機能検査には機能画像検査と、神経の電気活動を調べる生理機能検査とがあります。機能画像検査としては、ポジトロン断層撮影(PET)や機能的MRI(fMRI)といった検査があり、ごく簡単な運動中や言葉をしゃべっているときの脳活動を調べることができます。
しかし、PETやfMRIは基本的に安静に寝ている状態でないと検査ができないため、リハビリテーションの評価に使用するには、おこなえる課題が限られてきます。実際の歩行中や、リハビリテーション中のダイナミックな動きの最中の脳活動の変化を調べるには、前回までに紹介した、近赤外線光で測定するfNIRSという検査もあります。
生理機能検査には脳の電気活動をみて形態や機能の異常を調べる脳波検査や、手足を動かしている神経や筋肉の電気活動を調べる神経伝導検査、および筋電図検査があります。
そのなかのひとつに以前紹介した経頭蓋磁気刺激法(TMS)があります。これは円形や8の字形のコイルを頭の表面に当てて磁気を流すことで、脳表面の神経細胞へ結合しているシナプスを刺激し、その命令が伝わって手足が動くまでの時間や反応の大きさをみるというもので、脳からの運動神経の通り具合を調べる検査です。
fNIRSを使ったり、磁気刺激を使ったりすることは、脳卒中により損傷を受けた脳の働きを知り、どの程度の予備能力が発揮できそうか、可能性をさぐるための一つの目安になります。
これらには課題があります。検査結果をどう解釈していくか定まったものはありません。また、これらの検査手法はリハビリテーションの予後を正確に予測できる手段でもありません。一歩ずついろいろな研究をして、方法と結果を積み重ねていかなければ、ほんとうに知りたいと思うことがわかるようにはなりません。このようなことを意識しながら検査や治療にのぞむ必要があります。
今回はここまでです。次回は「最新のリハビリテーションのために」というテーマでお話ししていきます。
脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院
院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)
〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10
TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com
こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。
前回は、「リハビリテーション病院での入院生活」についてお話ししました。
今回は、「脳卒中の症状と入院生活」についてお話ししていきます。
さて、脳卒中の主な症状を示します。脳や神経が傷ついてからだがうまく動かなくなった状態が運動麻痺で、もっともあらわれやすいものです。触覚や痛覚、温度感覚が低下する状態を感覚障害といいます。ほかにも、バランスをとったり細かい精密な動きが難しくなったりする小脳失調、ろれつが回りにくくなる構音障害、食べ物の飲み込みが悪くなる嚥下障害、言葉の理解や表現が困難になる失語症や、身の回りの状況や日時の感覚がわからなくなったり、見えるものや聞こえるものの認知が悪くなったりする高次脳機能障害(記憶・思考・行動などの複雑なレベルの脳機能の障害のこと)などがあります。
脳卒中と一言で表しても、障害を受けた脳の部位や大きさにより起こる症状はさまざまです。また、前にあげた障害は一つだけでなく複雑に組み合わさる上、さらには本人のもともとの体力や持病もあると、症状は千差万別となります。
また、脳卒中により引き起こされる合併症もさまざまなものがあげられます。転院の時点ですでに伴っていることもあるし、入院期間中に新たに出てくることもあります。なかにはリハビリテーションの続行が困難になったり、せっかくの快復を妨げたりする合併症もあるので、つねに気をつけて対処していく必要があります。患者さんをたくさん診察して経験を積み、一人ひとりを深く観察し、どのような機能が伸ばせそうで、逆にどのような合併症が起こりうるか予測をたてて、早めに対応していこうとすることは医師の立場として重要なことです。
このような機能障害から引き起こされる、日常生活動作の不具合の確認もおこなっていきます。これを能力障害とよびます。日常生活動作とは、トイレ、更衣、歯みがき、入浴などがあげられます。麻痺の強い人はベッド上で寝たきりのために、実際はどれだけ身の回りのことができるか試さないまま転院してくる場合も少なくありません。
発症前の日常生活や家屋の状況についても確認します。日常生活については就業していた場合は職務内容や通勤手段、お年寄りなら発症前の活動状況は重要です。身の回りのことが自分でできていたか、趣味や好きなことは何か、外出をしていたか、家の周りに坂道や階段はないか、家のトイレやお風呂や階段の構造は使いやすいものか、部屋の敷居に段差はないか、などといったことも調べます。
今回はここまでです。次回は「リハビリテーション病院における検査」というテーマでお話ししていきます。
脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院
院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)
〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10
TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com
こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。
前回は、「脳卒中リハビリテーション入院の実際」についてお話ししました。
今回は、「リハビリテーション病院での入院生活」についてお話ししていきます。
さて、リハビリテーション病院での入院生活を、順を追って見ていきましょう。リハビリテーション病院の入院初日には、入念な診察をおこないます。患者さんのからだの状態を正確に知り、脳を調べ、症状と脳の働きの関係を理解し、将来を予測し、的確な治療を選ぶためです。
ある日突然脳卒中になり病院(おもに急性期の病院)に運ばれ、患者さん本人も家族も無我夢中で過ごします。急性期治療にひと区切りついた時点で、患者さんはリハビリテーション病院に転院してくることになります。この転院の日が脳卒中を発症して初めての外出になる場合も多々あります。
病院の玄関に到着すると、担当看護師が迎え、入院病棟へ案内します。挨拶から始まり、家族同伴のもとで最初の診察をします。あらかじめ急性期病院から紹介状をもらっているので大事な医療情報はほぼ把握していますが、患者さん本人と家族から生の声を聞き、発症時の状況や入院生活のことを把握することにしています。それはコミュニケーションでもあり、当時の状況をきちんと説明できるかどうかが病状の重さを推し量る一つにもなり、また語感や口調から病気に対する気持ちや現状の快不快を知ることができます。また急性期の重点管理中には、本人が同席できず家族だけが病状説明を受けた状況もありえますし、当初の意識はぼんやりしていて説明の内容を覚えていないことも少なくありません。
つぎに、からだに受けたダメージの診察をしながら、医師は発症の原因になった病巣との関連と、時期による変化を推測します。昨今は診断技術はめざましく進歩しましたが、やはり症状を詳しく観察して、病巣と矛盾がないか、また症状の変化を推し量ることは大変重要です。
今回はここまでです。次回は「脳卒中の症状と入院生活」というテーマでお話ししていきます。
脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院
院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)
〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10
TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com
こんにちは、大阪市西成区天下茶屋の康祐堂鍼灸院です。
前回は、「リハビリテーションで脳を変える」についてお話ししました。
今回は、「脳卒中リハビリテーション入院の実際」についてお話ししていきます。
さて、脳卒中によっていったん失われた機能が、リハビリテーションで少しずつよくなり、脳も変わっていくことは前回までに紹介しましたが、実際のリハビリテーションはどのように進んでいくのでしょう? 入院から退院までスタッフがどのように患者さんと関わっていくのか、その実際の流れを解説します。
脳卒中を発症すると、急性期病院に運ばれて、脳卒中の診断を受け治療を受けます。最近は早めにリハビリテーションを始める施設も増えてきました。しかし天敵やモニターがつながっていることが多いので、セラピストがベッドサイドに出向いて全身に負担をかけない範囲で関節を動かすような簡単なリハビリテーションとなります。
リハビリテーション専門病院に転院してきたら、検査や評価をしながら、スタッフはチームを組んで多角的にリハビリテーションをおこないます。理学療法士は歩行や移動手段、バランス訓練などを担当します。作業療法士は上肢の動きの訓練や更衣、食事、家事、入浴などの日常生活動作のリハビリテーションをおこないます。言語聴覚士は発音や嚥下(えんげ)の訓練が仕事です。そして、看護師は、病状を観察したり、リハビリテーションの成果が病棟での日常生活動作に定着できるよう支援していきます。リハビリテーションの進行にともなって、家族に対する指導も進めていきます。自宅の生活にスムーズに移行するためには家族の理解と支援がとても重要だからです。ソーシャルワーカーは退院のために必要な社会サービスの利用案内を、入院時点から始め、介護保険のケアマネージャーへ橋渡しをしていきます。
入院も後半にさしかかれば、必要に応じて手すりの設置や段差の解消など自宅を改修したうえで外泊訓練をし、生活の不自由を少なくしていきます。この際セラピストが患者さんと一緒に自宅へうかがい、ケアマネージャーやリフォーム業者同席の上、日常生活動作を実際にシミュレートしながら自宅内の改修内容や退院後のサービス利用を話し合う訪問指導をおこなうこともあります。再発予防のための服薬には薬剤師が、食事内容には栄養士が、それぞれに指導に入って支援していきます。
医師は症状を安定させ、合併症の予防など全身管理をしながらチームを統括していきます。入院時から定期的にカンファレンス(チーム会議)をおこない、チームの方向性が退院に向けて一致できるよう各スタッフが情報や意見を交換します。
今回はここまでです。次回は「リハビリテーション病院での入院生活」というテーマでお話ししていきます。
脳梗塞、脳卒中、片麻痺なら大阪市西成区天下茶屋の康祐堂あけぼの漢方鍼灸院
院長 冨田 祥史(山元式新頭針療法 YNSA学会 評議員)
〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋2-21-10
TEL&FAX 06-6659-0207 Email: mail@ynsa-japan.com