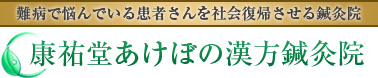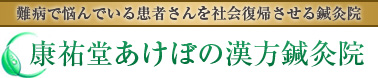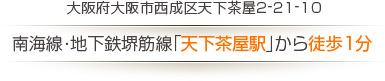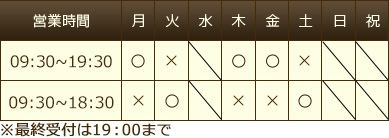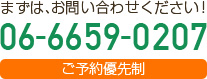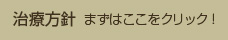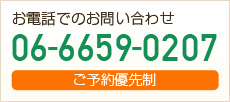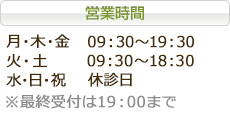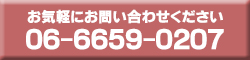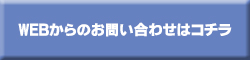パーキンソン病⑦西洋医学治療法
パーキンソン病の治療法には、L-ドパによるドーパミン補充療法を中心とした薬物療法、刺激発生装置や持続注入ポンプなどの機器(デバイス)を用いるデバイス補助療法などがあります。そして、これらの治療法と同じくらい重要な役割を果たすのが、患者さん自身が楽しみながら継続して行うリハビリテーションです。
薬物療法
パーキンソン病は、L-ドパとドーパミンアゴニストを中心に、複数の薬を組み合わせて治療しますので、それぞれの薬の目的をよく理解してのむことが大切です。薬の形状も飲み薬だけでなく、貼付剤や自己注射剤のような投与方法もあります。また、パーキンソン病の治療薬以外の薬を併用するときには、飲み合わせに注意することも大切です。
私たちの体は、大脳皮質からの指令が筋肉に伝わることによって動いています。この大脳皮質の指令を調節し、体の動きをスムーズにしているのがドーパミンです。 パーキンソン病は、中脳の黒質にあるドーパミン神経細胞がこわれて、作られるドーパミンが減ることによって発症します。
ドーパミンが減ると、体が動きにくくなったり、ふるえが起こりやすくなったりします。ドーパミン神経細胞は、年齢とともに自然に減っていきますが、パーキンソン病の患者さんの場合は、健康な人に比べてより速いスピードで減っていきます。
ドーパミン細胞が急激に減っていく理由はわかっていませんが、パーキンソン病の発症にはドパミン細胞の中でαシヌクレインというタンパク質が凝集することに関連していると考えられています。食事や職業、住んでいる地域など、原因となる特別な理由はありません。また、稀に家族性に発症し、その遺伝子が特定される場合もありますが、患者さんのほとんどは孤発性であり、遺伝性を示しません。
高齢になるほどパーキンソン病を発症する割合が増えますが、40歳以下で発症することもあり若年性パーキンソン病と呼んでいます。なお、患者さんの数は10万人に100人~150人くらいですが、60歳以上では10万人に約1,000人と多くなっています。
パーキンソン病は、脳の中の神経の伝達物質であるドパミンを作る細胞(ドパミン神経細胞)が減ってしまうために起こる病気です。しかし、ドパミンが欠乏する病気はパーキンソン病の他にもあります。
「ドパミンが欠乏していてもパーキンソン病ではない病気」をまとめてパーキンソン症候群と呼びます。
パーキンソン症候群には、①脳細胞の病気と②脳細胞以外の病気・症状が含まれます。
①脳細胞の病気
○多系統萎縮症
多系統萎縮症ドパミン欠乏に加えて、自律神経が障害される病気。立ちくらみや失神発作、排尿障害、睡眠中のいびきや無呼吸などの症状が特徴。
○進行性核上性麻痺
進行性核上性麻痺脳幹の神経細胞が減少する病気。早期からのすくみ足や後ろ向きに転びやすいことが特徴。進むと目の動きが悪くなり、認知機能が低下。
○大脳皮質基底核変性症
大脳皮質基底核変性症パーキンソン病の症状と大脳皮質の症状が見られる病気。片方の手足が固まったり、単純動作は出来ても複雑な動作が出来ない、意図通りにならないといった症状が特徴。
②脳細胞以外の病気・症状
○脳卒中
加齢などによって血管がもろくなり(動脈硬化)、血管が詰まったり(脳梗塞)、出血して(脳出血)脳が障害されて起こる病気。
○薬剤性
薬がドパミンの働きを妨げることでパーキンソン病に類似した症状が起こる病態。抗精神病薬などで発生しやすい。
運動症状として、初発症状は振戦が最も多く、次に動作の拙劣さが続きます。中には痛みで発症する症例もあり、五十肩だと思って治療していたが良くならず、そのうち振戦が出現して診断がつくこともまれではないです。しかし、姿勢反射障害やすくみ足で発症することはないです。症状の左右差があることが多いです。
動作は全般的に遅く拙劣となりますが、椅子からの起立時やベッド上での体位変換時に目立つことが多いです。表情は変化に乏しく(仮面様顔貌)、言葉は単調で低くなり、なにげない自然な動作が減少します。歩行は前傾前屈姿勢で、前後にも横方向にも歩幅が狭く、歩行速度は遅くなります。進行例では、歩行時に足が地面に張り付いて離れなくなり、いわゆるすくみ足というものが見られます。方向転換するときや狭い場所を通過するときに障害が目立ちます。
パーキンソン病では上記の運動症状に加えて、意欲の低下、認知機能障害、幻視、幻覚、妄想などの多彩な非運動症状が認められます。 このほか睡眠障害、自律神経障害(便秘、頻尿、発汗異常、起立性低血圧)、嗅覚の低下、痛みやしびれ、浮腫など様々な症状を伴うことが知られるようになり、パーキンソン病は単に錐体外路疾患ではなく、パーキンソン複合病態として認識すべきとの考えが提唱されています。
身体機能の異常
○歩行障害
前かがみの姿勢で小刻みにすり足で歩く
歩き出しの一歩が踏み出せない(すくみ足)
歩いているとだんだんスピードが速まる(加速歩行) など
姿勢の異常
腰が曲がる(前傾姿勢)、ななめに傾いてしまう、首が下がる など
無表情
まばたきが減る、表情がなくなる「仮面様顔貌」 など
嚥下障害
食べ物が飲み込みにくくなる
字の変化
字が小さくなる、ふるえる、字を書いているうちにだんだん小さくなる
自律神経の異常
○便秘
初期からあらわれ、90%以上の患者さんにみられる
起立性低血圧、立ちくらみ など
排尿障害
夜間に何度もトイレに起きる、尿が漏れてしまう など
精神・認知の異常
うつ状態、不眠、何をしても楽しくない など
認知症
計画をたてることがおっくうになる など
感覚の異常
幻覚・妄想、ないものが見える(幻覚)、根拠のない思い込み(妄想) など
痛み・しびれ
関節痛、筋肉痛、手足のしびれや痛み など
嗅覚の低下
においが鈍くなる
睡眠障害
中途覚醒、朝起きるときの筋肉の痛みやこわばり など
パーキンソン病の4大症状
①手足が震える[振戦(しんせん)]
座って何もしていない時や寝ている時に、手足が小刻みに震えます。動いたり、何かしようとするときには、震えが止まることが多いのが特徴です。パーキンソン病の最も代表的な症状です。
② 筋肉がこわばる[筋固縮(きんこしゅく)]
筋肉がこわばり、身体がスムーズに動かなくなります。歯車のように規則的な動きになる場合を歯車現象、こわばりが続く場合を鉛管(えんかん)現象と呼びます。
③動きが鈍くなる[無動、寡動(むどう・かどう)]
素早い動作ができなくなります。動きが小さくなり、歩いているときにもほとんど手を振らなくなります。一度にいくつもの動作をしようとすると、さらに動きが鈍くなります。
④身体のバランスがとりにくくなる[姿勢反射障害(しせいはんしゃしょうがい)]
立っているとき、軽く押されるとバランスを崩してしまいます。バランスを崩すと元に戻しづらくなり、転んでしまうことがあります。これは進行すると出てくる症状です。(重症度分類でヤールⅢ度と呼ばれます。)
パーキンソン病は、脳の異常のために、体の動きに障害があらわれる病気です。
現在、日本には約20万人の患者さんがいるといわれています。高齢者に多くみられる病気ですが、若い人でも発症することがあり、若年性パーキンソン病と呼ばれます。
振戦(ふるえ)、動作緩慢、筋強剛(筋固縮)、姿勢保持障害(転びやすいこと)を主な運動症状とする病気です。症状には、体の片側から出始め、次第に反対側に広がっていくという特徴があり、ゆっくりと進行します。
パーキンソン病になると運動障害が現れるため、動くのが億劫になって生活の質が下がり、最終的には寝たきりになってしまう人もいます。
パーキンソン病は50~65歳で発症することが多く、高齢になるほど発病する確率が高まるといわれています。そのため、社会の高齢化がこれから進むにつれて患者数も増加すると予想されています。
塩分を控える12カ条
①薄味に慣れる
塩味の薄い食事に慣れることが第一歩です。昆布やかつおぶしなどで、だしをとると薄味でも風味豊かにおいしく食べることができます。また、新鮮な食材を利用して、薄味で素材の味を楽しむのもよいでしょう。
②漬け物・汁物の量に気をつけて
塩分の多い漬け物や汁物は、食べる回数と量を減らしましょう。漬け物は浅漬けか、塩出ししたものにします。汁物では野菜などの具の多いものにすれば、1回にとる汁の量が少なくなります。麺類を食べるときは、汁は残すようにします。
③効果的に塩味を
献立にはいろいろな味付けを利用し、塩味は効果的に使うようにしましょう。塩は食品の表面にさっとふりかけると少なくても塩分を感じることができます。
④「かけて食べる」より 「つけて食べる」
しょう油やソースなどは、かけて食べるより、つけて食べたほうが塩分の摂取量が少なくてすみます。
⑤酸味を上手に使いましょう
酸味を上手に使って、献立の味付けに変化をつけると、塩分を減らすことができます。レモン、スダチ、カボスなどの柑橘類や酢などを和え物や焼き物に利用しましょう。
⑥香辛料をふんだんに
トウガラシやコショウ、カレー粉などの香辛料を上手に使って味付けに変化をつけるのも、塩分を控える工夫の1つです。
⑦香りを利用して
ゆず、シソ、ミョウガ、ハーブなどの香りのある野菜、海苔、かつお節などを加えると、薄味のメニューに変化もつきます。
⑧香ばしさも味方です
香ばしさもまた塩分のとりすぎを抑えてくれます。焼き物にする、炒った胡麻やくるみなどで和えるなど、調理に利用しましょう。
⑨油の味を利用して
揚げ物、油炒めなど、油の味を利用して食べるのもよいでしょう。ゴマ油やオリーブオイルを、食べる前に少しかけることで風味が増し、おいしく食べられます。ただし、脂質のとりすぎにならないように、油を使ったメニューばかりにならないよう気をつけましょう。
⑩酒の肴に注意
酒の肴に合う料理は塩分が多く含まれるものが多いので、少量にしましょう。
⑪練り製品・加工食品には気をつけて
かまぼこ、はんぺん、薩摩揚げなど魚の練り製品や、ハムやベーコンといった肉の加工食品も塩分の多い食品です。食べる量に気をつけましょう。
⑫食べすぎないように
せっかくの薄味の料理でも、たくさん食べれば塩分の量もカロリーも多くなります。食べすぎないように気をつけましょう。減塩しょう油や減塩みそも、使う量が多ければ塩分も増えます。使いすぎては意味がありません。
①質と量のバランスの良い食事を取る
健康な体を維持し十分な活動をするためには、主食、主菜、副菜を揃えて食べましょう。
②標準体重を維持する
太り過ぎも、やせ過ぎもよくありません。どちらも高血圧や動脈硬化症などの原因になります。適正な体重に近づけるようにしましょう。
③動物性脂肪の取り過ぎに注意する
血液中のコレステロ-ルの増加を予防するうえで大切です。牛肉や豚肉、鶏肉などの肉類の脂肪の多い部分は控えましょう。油は、バターやラードなどは控え植物性の油を使用しましょう。
④良質のたんぱく質は十分に取る
脂肪の少ない肉類、魚介類、卵、大豆製品、牛乳・乳製品などは不足しないよう毎日十分に取りましょう。
⑤食塩は控えめにする
食塩の取り過ぎは高血圧など脳出血の原因になる病気を助長させます。食塩を多く含む加工食品を避け、食塩は1日男性7.5グラム・女性6.5グラム未満を目標に、薄い味付けに慣れましょう。
⑥野菜、果物、海藻は十分に取る
これらの食品には、ビタミンやミネラル、食物繊維が豊富に含まれ、便通を整えるとともにカリウムは体内の余分なナトリウムを体外に排泄する働きを持っています。新鮮な物を毎日十分取るように努めましょう。
⑦食事時間は規則正しく、3食を平均して食べる
朝、昼、夕食ともバランス良く食べ、落ち着いた気分で楽しく食事ができれば最高です。
⑧アルコ-ルは適量を飲む
アルコールは動脈硬化の危険因子です。深酒は厳禁、適量を守って程々にします。酒のさかなは塩辛いものを避け、脂肪の少ない肉や魚、そして豆腐や野菜などをバランスよく取り合わせましょう。
高血圧の人は特に注意しましょう!脳出血の予防法
血圧が上がらないように日常生活を過ごすことがいちばんの予防となります。
①減塩を心がけた食事
適切な塩分量には個人差もありますが、日本高血圧学会の推奨する塩分摂取量は1日6グラムです。
もう少し味を濃くしたいというときには、すだちやレモンなど柑橘系の香りを加えたり、薬味を添えることで味にバリエーションができます。
②怒責は禁物、便秘にならないようにする
便が出にくいと怒責をかけて排便するため、脳の血管に負担がかかります。
日ごろから水分を充分にとるように意識したり、便秘傾向の人はかかりつけ医に相談しましょう。
③入浴は38~42℃で10分以内に
入浴時の熱いお湯は急な血圧の上昇の原因になり、血管に負担をかけます。
低めのお湯で徐々にあたたまることを心がけ、のぼせないように長湯も控えましょう。
また冬場は、リビングと浴室の室温差によって血圧が大きく変動する「ヒートショック」にも注意が必要です。
④激しい運動は避け適度な散歩程度
激しい運動は血圧の上昇を招きます。適度な運動はリラックス効果もあるので、心地よいと思えるくらいの散歩をしましょう。
もちろん、疲れたときは無理をせずに休息をしてください。