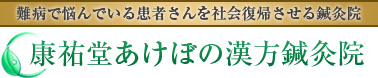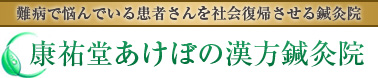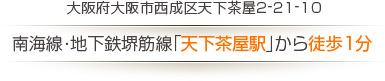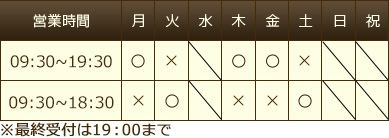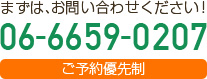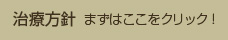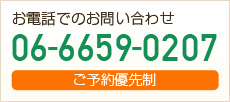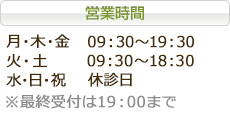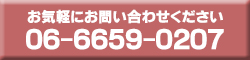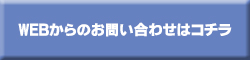脳出血⑦日常生活で気をつけること
脳出血を予防するためには何より高血圧の管理に尽きます。血圧を毎日測って高い状態(大体140/80mmHg位まで)が続かないように注意する必要があります。
血圧を下げる方法は、大きく二つあります。一つは生活習慣の見直しです。「塩分のとりすぎ」や「過度の飲酒」「喫煙」「肥満」「ストレス」など、生活習慣に気を付けましょう。塩分を抑えたバランスのいい食事を摂り、適度な運動を心がけてください。
もう一つは「薬物治療」です。血管を拡張させて血圧を下げる「血管拡張薬」や、尿量を増加して血液量を減らす「利尿剤」など「降圧剤」にはさまざまな種類があります。高血圧の方は、ぜひ、血圧の専門医を受診し、自分に一番合うタイプの降圧剤を処方してもらってください。
薬物療法と外科手術があり、出血量や症状の程度、治療中の容態の変化などによって選択される治療法は異なります。高血圧によって引き起こされた脳出血であれば、まずは早急に血圧を下げることが肝要です。出血量が少なく症状が軽度の場合は、点滴によって降圧剤を投与していきます。血圧を下げることによって、脳内にできる血の塊を大きくしないようにしたり、血管から再出血する状態を防ぐ作用があります。状況によっては、さらに脳のむくみをとる薬も用いります。一方、出血の量が多く症状が重かったり、病状の進行が考えられる場合は、血の塊を取り除いたり、脳の中にたまった水を外に出して脳の圧迫を減らしたりする外科手術を行います。ただし手術によって脳にダメージを与えることもあるため、一般的には、あくまでも脳にできた血の塊が大きい場合に選択されることが多いです。
一般的に小脳出血、被殻出血に対しては積極的に緊急手術を施行しますが、視床出血では脳深部にあるため緊急手術の適応となることは少なく、保存的に様子をみることが多いです。こういった患者では、慢性期の血腫がある程度やわらかくなった時期に、神経症状の早期改善を期待して局所麻酔下に、穿刺による吸引除去術を行うことが可能です。
近年では内視鏡技術の進歩により、開頭せず、100円玉ぐらいの穴を頭蓋骨に開けるだけで、大きな脳内血腫を摘出する技術も発展しています。
①被殻出血
主に高血圧を原因として、大脳の深い位置で出血するタイプです。出血したのが右脳であれば左半身に、左脳であれば右半身に麻痺、しびれが生じます。左脳で起こった脳出血は、言語障害を伴うことも多くなります。
②視床出血
主に高血圧を原因として、大脳の最深部で出血するタイプです。出血したのが右脳であれば左半身に、左脳であれば右半身に麻痺、しびれが生じます。
③皮質下出血
主に脳動静脈奇形など、血管の病変を原因として、大脳の表層で出血するタイプです。
出血した位置により、さまざまな症状をきたします。
④小脳出血
主に高血圧を原因として、小脳で出血するタイプです。ふらつきなどの症状を伴います。
出血がひどくなると、脳幹を圧迫します。
⑤脳幹出血(橋出血)
主に高血圧を原因として、脳幹部で出血するタイプです。出血が少量であっても、意識の低下などをきたすことが多くなります。
原因としては、高血圧が最も多いです。長い間、慢性高血圧をそのままにしておくと、脳内の細い動脈が徐々に弱くなっていき、最終的には血管が破れて血液が脳内に流れ出てしまいます。
また高齢者に限ると、脳アミロイド血管症と呼ばれる血管の疾患も脳出血を引き起こします。これはアミロイドというタンパク質が脳内に蓄積されることが原因となり、繰り返し脳出血を起こすことにつながるものです。アミロイドの蓄積は脳出血に加え、認知症の原因の1つでもあります。
他には、動脈瘤などの血管の異常、脳腫瘍、肝臓疾患などが原因となることもあります。血液をサラサラにする目的の抗凝固薬も、過剰に投与されると脳出血のリスクがあるので注意が必要です。
また、高血圧に伴う「動脈硬化」も原因のひとつに挙げられます。動脈硬化が起こると、血管がもろくなります。その結果、血管の高血圧に対する耐久力が下がり、出血を起こしやすくなってしまいます。
高血圧に加えて、血管(脳内小動脈)に血管壊死と言う変化が起きると、それが小動脈瘤に進展し、何らかの誘因によって破壊して脳出血を起こすと言われています。この他血管腫、動静脈奇形、硬膜動静脈瘻、脳腫瘍なども原因となります。
④小脳出血
小脳は、脳幹(大脳と脊髄をつなぐ器官)の背後に位置しています。知覚と運動機能を統合し、平衡感覚や筋緊張などを調節する役割を持っています。この部分からの出血は、脳出血の約10%を占めています。
ここで出血が起こると、突然の頭痛やめまい、嘔吐などが症状として現れます。また、小脳が運動機能をつかさどっている関係上、起立・歩行障がいなどの「運動失調」が起こることもあります。うまく立てない、うまく歩けないといった運動機能の異常が見られます。また、血腫が大きい場合には脳幹が圧迫され、命に危険がおよぶことがあります。
⑤橋出血
「橋」は、中枢神経系を構成する重要な部位が集まる「脳幹」の一部に含まれる部位です。脳幹は大脳と脊髄をつなぎ、脳が処理した情報を脊髄に伝えて実際の行動につなげていますが、橋には顔の筋肉や眼球を動かしたり、呼吸を調整したりする働きなど、生命活動の維持に重要な役割を担っています。
この部分からの出血は、脳出血の約10%を占めています。この部分で出血が起こると、脳幹部にある「橋」は生命維持に必要な機能を持っていることから、橋出血は重症に至ることが多く、頭痛や片麻痺、意識障害などが症状として現れます。また、手足が動かなくなる四肢の麻痺、眼球の向きが左右でバラバラになるなどの異常を起こす「外転神経麻痺」が見られることもあります。瞳孔が小さくなる「縮瞳」などが起こったり、急速に昏睡状態となり、命に危険がおよぶこともあります。
①被殻出血
「被殻」は、大脳の中央部に左右1対あり、身体の運動調節や筋緊張、学習や記憶などの役割を持っています。この部分からの出血は最も高く、脳出血の約40~50%を占めています。
被殻出血の症状として、頭痛や体の半身が麻痺を起こす「片麻痺」、感覚障がい、言葉の理解や話すことが不自由になる失語症や構音障がい、顔の片側がゆがんでしまう「顔面神経麻痺」などがあります。
②視床出血
「視床」は、大脳半球と中脳の間にある間脳の左右に1対あり、触覚や痛覚などのさまざまな感覚を集約する役割を担っています。この部分からの出血は、被殻に次いで多い脳出血の約30%を占めています。視床は視覚や聴覚などで得た情報を集め、感覚中枢に送り届ける役割を担います。
この部分で出血が起こると、頭痛や片麻痺、顔面神経麻痺に加えて意識障がい、感覚障がいや、半身の激しい痛みが起こることがあります。また、眼球が下内側をみるような位置になったりするのも特徴です。
③皮質下出血
「皮質下」出血とは、大脳半球の表面を覆う「大脳皮質」の下で起こる脳出血です。脳出血の約10~20%を占めています。
「頭頂葉」「前頭葉」「側頭葉」などさまざまな部位で起こりますが、症状としては、いずれの場合も頭痛や痙攣、片麻痺、構音障がい、また五感に異常が見られる感覚障害などが挙げられます。そのほか片目、あるいは両目の視野の半分が欠けてしまう「半盲」も症状として現れます。
脳出血は残念ながら、はっきりとした前兆はありません。頭痛や目の見えにくさを訴える方もいらっしゃいますが、多くありません。ただ、出血の起こる脳の部位によって異なることがわかっています。
出血した部位や量によって症状は異なりますが、主に片側の手足の麻痺やしびれ、しゃべりにくさ、歩きにくさといった運動の症状、頭痛や強いめまい、吐き気や嘔吐といった感覚の症状などが認められます。 脳梗塞と似た症状のため、見分けることが難しいです。 少しずつ悪化することはまれで、短時間の間に症状が変化することが多いのも脳梗塞と同様です。
出血量が多かったり、生命維持に重要な部分に出血が起こったりすると、意識障害を引き起こし、死に至るケースもあります。出血した箇所の脳が炎症を起こして腫れてくると、さらに症状が悪化することにもつながります。
塩分のないところに高血圧はないので、塩分を控えめにしましょう。
血圧を下げるポイントは、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどの微量元素(ミネラル)を摂取することです。
魚の油に含まれるEPAやDHAには動脈硬化を抑えて脳梗塞を予防する効果があります。またEPAには血液をサラサラにする効果、DHAには頭を良くする効果もあります。
納豆に含まれるナットウキナーゼには、血栓を溶かして脳梗塞を予防する効果があります。
梅干やレモンなどのすっぱい食べ物に含まれるクエン酸は血液をサラサラにして脳梗塞を予防する効果があります。
体内で出来る有害な活性酸素の害を打ち消す抗酸化物資(スカベンジャー)を積極的に摂取して動脈硬化を防ぎましょう。それにはビタミンE、ビタミンC、カロチンなどがあります。
大量の飲酒、1日に、1合を超える日本酒、中びん1本を超えるビール、ダブルで一杯を超えるウイスキーを飲む人は特に気をつけましょう。
脳梗塞10カ条
①手始めに高血圧から治しましょう
②糖尿病放っておいたら悔い残る
③不整脈見つかり次第すぐ受診
④予防にはタバコを止める意思を持て
⑤アルコール控えめは薬過ぎれば毒
⑥高すぎるコレステロールも 見逃すな
⑦お食事の塩分、脂肪も控えめに
⑧体力に合った運動続けよう
⑨万病の引き金になる太りすぎ
⑩脳卒中起きたらすぐに病院へ
☆喫煙習慣=タバコを吸う人は吸わない人に比べ、はるかに脳梗塞で死亡する人が多いです。
☆運動不足=食事で摂ったエネルギーを消費しきれないので肥満につながります。さらに糖尿病や脂質異常症を引き起こしたりもします。
☆肥満=肥満は高血圧や糖尿病の原因になり得ます。間接的にではありますが、脳梗塞の危険因子です。
☆過度のストレス=日々のストレス、イライラに対抗するために、タバコをスパスパ、お酒をガブガブ。脳梗塞に限らず、身体にいいはずがありません。
脳梗塞は突然に起こる病気、かかってからしまったと思っても手遅れ、そこで普段から予防しておくことが大切です。
突然に、「半身の手足が動きにくくなった」、「半身の手足あるいは顔面がしびれる」、「ろれつが回りにくくなって、うまくしゃべれない」などの症状が起こった時は脳梗塞が疑わしいので、すぐに病院へ行きましょう。その他、「急に視野が欠けた、見えなくなった」、「めまいがした」などと言う症状も要注意です。
脳梗塞は、朝、起きた時に気付くことが多いです。朝、起きた時に以上のような症状に気付いた時は、脳梗塞の始まりかもしれません。様子を見ないで、すぐに病院へ行きましょう。
脳梗塞は夏に多いです。その理由は暑さのせいで汗をかいて脱水、つまり血液がドロドロになりやすいからなのです。炎天下を避け、汗をかいたら十分な水分補給をしましょう。
心臓の不整脈から起こる脳梗塞が増えています。動悸がしたら、心房細動など、心配な不整脈でないかどうか調べてもらいましょう。
脳梗塞の最大の危険因子は高血圧です。次に高脂血症(血液中のコレステロールが高い)、糖尿病があります。このような病気にかかっていないか時々チエックして、早めに治しておくことが、脳梗塞の予防に一番、大切です。高血圧、高脂血症、糖尿病を放っておくと、将来、脳梗塞や心筋梗塞にかかることになります。しかし血圧が高くても、血液中のコレステロールが高くても、あるいは血糖が上がっていても、普通、痛くもかゆくもないので、治療を受けようという気になりにくいことに注意してください。タバコを吸っていると多血症、すなわち血液が濃く、ドロドロとした状態になり、脳梗塞にかかりやすくなることにも注意が必要です。
血液の流れを悪くする悪玉コレステロール対策もしましょう。適度な運動も欠かせません。長く続けるためには、あまり負担にならないウオーキングやジョギング、水泳などがおすすめです。これらのいわゆる有酸素運動 (たくさんの酸素を使って長時間続ける運動のこと) には、脂肪を燃焼させる働きがあります。特にウォーキングは、「歩く」という日常の動作ですので、すんなり始められると思います。脂肪を燃やすことはもちろん、悪玉コレステロールを減らしたり、血液量が増えるため血管の弾力性を強化することにもつながります。